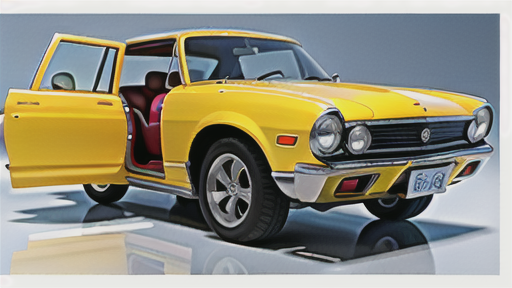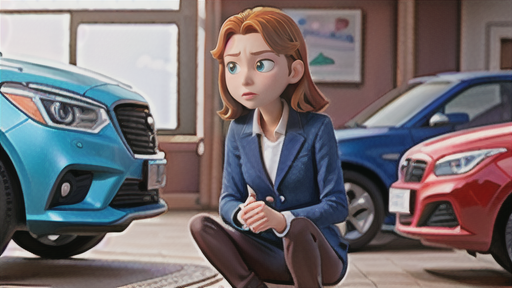駆動系
駆動系 タイヤの動的負荷半径:知られざる性能への影響
車は、路面と接するタイヤによって支えられ、その回転によって前に進みます。このタイヤの働きを理解する上で、「動的負荷半径」という考え方が重要になります。タイヤは、ただ丸いゴムの塊ではなく、路面からの力を受け、変形しながら回転しています。そのため、実際のタイヤの振る舞いは、単純な円の回転とは異なります。動的負荷半径とは、タイヤが実際にどれだけ回転し、どれだけ進んだかという、実際の移動量から計算されるタイヤの有効半径のことです。平たく言えば、タイヤを一回転させた時に車がどれだけ進むかを計測し、その値を円周率の二倍で割ることで求められます。例えば、タイヤを一回転させたら車が2メートル進んだとします。この時、円周率の二倍は約6.28なので、2メートルを6.28で割ると、動的負荷半径は約0.32メートルとなります。この動的負荷半径は、タイヤの空気圧や車の重さ、路面の状態など、様々な要因によって変化します。例えば、空気圧が低いとタイヤはより潰れた状態になり、動的負荷半径は小さくなります。逆に、空気圧が高いとタイヤはより膨らんだ状態になり、動的負荷半径は大きくなります。また、重い荷物を積むとタイヤは路面に押し付けられて変形し、動的負荷半径は小さくなります。動的負荷半径を理解することは、車の速度計や走行距離計の精度を保つ上で重要です。これらの計器は、タイヤの回転数に基づいて速度や距離を計算しています。もし、動的負荷半径が想定と異なると、実際の速度や距離と計器の表示値にずれが生じてしまいます。例えば、タイヤの空気圧が低い状態で走行すると、動的負荷半径が小さくなり、実際の速度よりも計器の表示値が速くなってしまいます。このように、動的負荷半径はタイヤの性能を評価する上で非常に重要な指標となります。タイヤを選ぶ際や、車の整備を行う際には、動的負荷半径について理解しておくことが大切です。